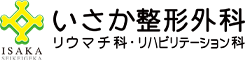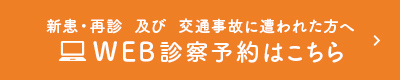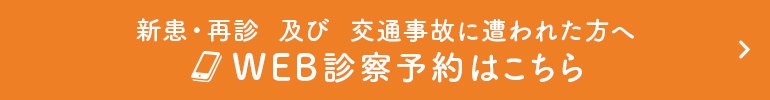変形性膝関節症とは

- 変形性膝関節症とは
- 変形性膝関節症は、長年の使いすぎにより膝関節内部の軟骨や骨がすり減り、骨同士が直接衝突することで膝の痛みや腫れなどの炎症症状が発生する膝に起こる病気です。
- 進行具合で症状が異なり、それぞれにおける治療法や予防対策も変わってきます。
- このページでは、変形性膝関節症に対する知識をつけていただくため、症状や治療法、日常生活での心がけや予防法について解説をさせていただきます。
- 年齢を重ねても、皆様が健康的なライフスタイルを築いていけるきっかけになれば幸いです!
変形性膝関節症の症状
 変形性膝関節症の症状
変形性膝関節症の症状
-
- 代表的な症状
- 膝周囲の痛みやこわばり
- 関節の骨同士の長年の負荷や接触によって、軟骨や骨の痛みを引き起こします。特に、歩行時などに痛みが増します。
- 膝関節の腫れ・水がたまる
- 炎症反応によって、膝の周りに水がたまることがあります。
- 膝の変形
- 変形性膝関節症が進行すると、膝の形が変形して、O脚になることが特徴です。
- 膝関節の可動域制限や筋力低下
- 痛みや腫れなどで、膝関節の可動域が制限され、膝を曲げたり伸ばしたりするのが難しくなります。また、痛みなどによって運動量が減ることで筋力が低下してしまいます。
- 膝周囲の痛みやこわばり
- 進行度合別のよくある症状
- 初期症状
- 朝起きたときに、膝が固く感じたり、重くて動かしにくかったりするといったこわばりを感じるのが特徴です。いわゆる”膝の違和感”です。そこから徐々に、階段の上り下りや急な方向転換などをしたときに、膝関節の痛みが現れるようになります。初期症状の段階では、身体を動かし始めると自然と治るため、変形性膝関節症と気づかれない場合があります。しかし、これらの症状が放置されると、悪化する可能性があります。
- 中期症状
- 膝の痛みが治まりにくくなり、正座や深いしゃがみ込み、階段の上り下りがつらくなってきます。膝関節内部の炎症が進むと、熱感や腫れが生じることもあります。膝の変形が目立ってきたり(多くはO脚)、膝関節内の軟骨や骨がすり減って、歩行時に関節がきしむ音がしたり、足をついたときに痛みが発生する場合があります。
- 末期症状
- 最も重度の場合、関節軟骨が完全に消失し、骨が直接ぶつかってしまう状態です。この段階では、初期・中期症状がより悪化して、普段の歩行、立ち座り、しゃがんだりすることが非常に困難になります。それによって、日常生活にも支障が生じるため、生活の幅が狭くなり、運動量も減ってしまうことがあります。そして、運動量が減ることで可動域制限や筋力低下が顕著になり、運動ができなくなるという悪循環が生まれます。
- 初期症状
- 代表的な症状
変形性膝関節症の原因
- 変形性膝関節症の原因
- 変形性膝関節症の原因は、一次性のものと二次性のものに分類をされています。
- 一次性:明らかな原因がないもの
- 二次性:病気やケガなどの原因が明らかなもの
- 変形性膝関節症の多くの原因が一次性と言われております。
- 一次性の変形性膝関節症の原因
- 加齢による関節軟骨のすり減り
- 肥満(普通に歩くだけでも膝に体重の7倍の力が加わるため、体重が増えれば増えるほど、膝への負担は大きくなります。)
- 下肢アライメント(大腿骨と下腿骨の関節の形)
- 重労働の職業(膝への負担が大きい仕事)
- 遺伝・生活環境
- 性別(女性は男性より多く発症することがわかっています) など
- 二次性の変形性膝関節症の原因
- 過去の外傷
- 靭帯損傷(前十字靭帯損傷など)、半月板損傷、骨折
- その他疾患
- 炎症性疾患(リウマチ、化膿性関節炎など)、腫瘍性疾患(腫瘍性骨軟骨腫症など)、大腿骨顆部壊死など
- 過去の外傷
- 変形性膝関節症の原因は、一次性のものと二次性のものに分類をされています。
加齢
 膝関節表面の軟骨は加齢によって変性して傷付きやすくなります。その状態で負担がかかると、膝関節の軟骨が徐々に摩耗してしまい、変形性膝関節症の発症につながります。
膝関節表面の軟骨は加齢によって変性して傷付きやすくなります。その状態で負担がかかると、膝関節の軟骨が徐々に摩耗してしまい、変形性膝関節症の発症につながります。
肥満
 歩く際には膝に体重の約3倍という、とても大きな負荷がかかります。肥満で体重が重くなれば負担はそれだけ大きくなり、変形性膝関節症の発症・悪化のリスクが大幅に上昇します。
歩く際には膝に体重の約3倍という、とても大きな負荷がかかります。肥満で体重が重くなれば負担はそれだけ大きくなり、変形性膝関節症の発症・悪化のリスクが大幅に上昇します。
筋力低下
 筋力が高ければ歩行の際に外部からの衝撃や負担を受け止めて膝を支えられるため、膝関節への負担を軽減できます。筋力が低下すると衝撃のほとんどを膝関節が受けることになるため、摩耗が早く進んで変形性膝関節症の発症・悪化のリスクが上昇します。
筋力が高ければ歩行の際に外部からの衝撃や負担を受け止めて膝を支えられるため、膝関節への負担を軽減できます。筋力が低下すると衝撃のほとんどを膝関節が受けることになるため、摩耗が早く進んで変形性膝関節症の発症・悪化のリスクが上昇します。
変形性膝関節症の検査・診断
 変形性膝関節症の診断
変形性膝関節症の診断
-
- 当院における変形性膝関節症の診断は、主に問診・触診、画像診断で行います。
- 問診・触診
- 膝の痛みや腫れ、関節の動き、関節の不安定性などを問診や触診によって、膝の状態を確認させていただきます。
- 画像診断
- 膝関節の骨や軟骨の状態を正確に把握するためにMRI検査やレントゲン検査(X線撮影)を行います。MRI検査やレントゲン検査の画像をもとに変形性膝関節症の進行具合を診断いたします。
- 当院はMRIを院内に完備しているため、予約に空きがある場合は当日中にMRI検査を受けることができます。
- 血液検査
- 炎症の状態があまりにも悪い場合は、血液検査を実施することもあります。
- 関節穿刺を行い、関節液が濁っている場合に、偽痛風やリウマチ、化膿性膝関節炎などのその他の疾患との合併を確認します。
- 問診・触診
- 当院における変形性膝関節症の診断は、主に問診・触診、画像診断で行います。
変形性膝関節症の治療法
- 変形性膝関節症の治療法
- 変形性膝関節症は徐々に進行する疾患ですが、早めの治療をおすすめします。当ページではこれまでの従来の治療法に加え、これからの新たな治療法についてもご紹介をさせていただきます!
- これまでの従来の治療法
- 保存療法(手術をせず、まず最初に取り組む治療法)
- 理学療法士による運動療法(リハビリ)
- 変形性膝関節症が進行すると、痛みによって生活範囲が狭まると、膝を中心とした股関節、膝関節、足首の関節可動域が狭くなったり、筋力が低下して、関節が不安定になったりします。この状態になると、膝に負担がかかって痛みが増すといった悪循環を生みます。この悪循環を絶つために、運動療法を実施します。
- 定期的な有酸素運動や膝の筋肉を鍛えるための簡単な筋トレ、膝関節の可動域を広げるためのストレッチなどが変形性膝関節症の治療に効果的です。
- 引用元
- 「変形性膝関節症診療ガイドライン」日本整形外科学会HP
- https://www.joa.or.jp/topics/2023/files/guideline.pdf
- ただし、運動し過ぎると症状を悪化させる場合があるため、医師や理学療法士と相談しながら行うことをおすすめします。
- 薬の服用などで症状を軽減する方法(薬物療法)
- 内服薬
- 口から薬を摂取します。痛みや炎症を抑えるための非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)や解熱鎮痛剤、オピオイドなどの薬が用いられます。
- 外用薬
- 皮膚から薬の成分を吸収する、いわゆる塗り薬や貼り薬(湿布)です。非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)などを皮膚から吸収させて痛みや炎症を抑えます。
- 関節内注射
- 関節機能改善剤や炎症を抑える作用が強いステロイドが用いられます。ヒアルロン酸注射が一般的によく知られる注射での治療法になります。
- 引用元
- 「変形性膝関節症」日本臨床整形外科学会HP
- http://www.jcoa.gr.jp/health/clinic/knee/koa.pdf
- 関節機能改善剤や炎症を抑える作用が強いステロイドが用いられます。ヒアルロン酸注射が一般的によく知られる注射での治療法になります。
- 内服薬
- 理学療法士による運動療法(リハビリ)
- 手術療法
- 薬や運動療法を続けても症状が改善しない場合や痛み・変形がさらに悪化する場合は、人工膝関節置換術や高位脛骨骨切り術といった手術療法を検討していきます。
- 保存療法(手術をせず、まず最初に取り組む治療法)
- これからの新たな治療法
- 再生医療
- 保存療法から手術療法への決断が難しいというお悩みが多く、そんな多くの患者さんのお声に応えるため、保存療法と手術療法の中間的な位置付けとして、「再生医療」という治療の選択肢が増えました。
- 当院はPFC-FD™療法を導入しております。このようなお悩みを抱えている方はこちらをクリック
- バナーを挿入
- お悩み
- ヒアルロン酸注射で治療を続けているが、なかなか痛みが取れない方
- 現在の保存療法で、ひざの痛みが改善しない方
- 慢性的なひざの痛みが続いている方
- ひざの手術に抵抗がある方
- 再生医療
理学療法
 奥までしっかり温める・動きを改善する物理療法に加え、筋力をアップさせるトレーニングが重要になってきます。関節周囲の筋力をアップさせることで関節を安定させて、炎症や痛みを起こしにくくします。特に、大腿四頭筋の筋力強化は高い効果が見込めます。
奥までしっかり温める・動きを改善する物理療法に加え、筋力をアップさせるトレーニングが重要になってきます。関節周囲の筋力をアップさせることで関節を安定させて、炎症や痛みを起こしにくくします。特に、大腿四頭筋の筋力強化は高い効果が見込めます。
当院では膝の痛みの根本的な解消に有効とされるスクワットや膝を伸ばしたまま脚を上げるSLR訓練などをしっかり指導しています。無理のない範囲で行えるようにしていますので、安心してご相談ください。
薬物療法
 痛み止めの内服、湿布などの外用剤、坐薬などがあります。内服以外の痛み止めでも胃腸炎を起こすことがありますので慎重に投与し、胃腸症状が起こった場合には薬の種類を変更することで対応できます。また、胃薬を一緒に処方することもあります。
痛み止めの内服、湿布などの外用剤、坐薬などがあります。内服以外の痛み止めでも胃腸炎を起こすことがありますので慎重に投与し、胃腸症状が起こった場合には薬の種類を変更することで対応できます。また、胃薬を一緒に処方することもあります。
注射
 炎症が強い場合や短期間で鎮めたい場合にはステロイド(副腎皮質ホルモン)を入れた局所麻酔剤の注射が、高い効果を見込めます。軟骨の保護や関節のすべりを改善するヒアルロン酸ナトリウムは、痛みの改善につながることもあります。繰り返し行うことが可能です。
炎症が強い場合や短期間で鎮めたい場合にはステロイド(副腎皮質ホルモン)を入れた局所麻酔剤の注射が、高い効果を見込めます。軟骨の保護や関節のすべりを改善するヒアルロン酸ナトリウムは、痛みの改善につながることもあります。繰り返し行うことが可能です。
装具療法
 O脚が原因になって関節の内側に負担がかかっている場合には、足底板で体重が外側にかかるようにすることで症状を改善につながることがよくあります。足底板は靴の中敷きのような装具で、外側が少し高くなっています。
O脚が原因になって関節の内側に負担がかかっている場合には、足底板で体重が外側にかかるようにすることで症状を改善につながることがよくあります。足底板は靴の中敷きのような装具で、外側が少し高くなっています。