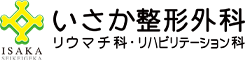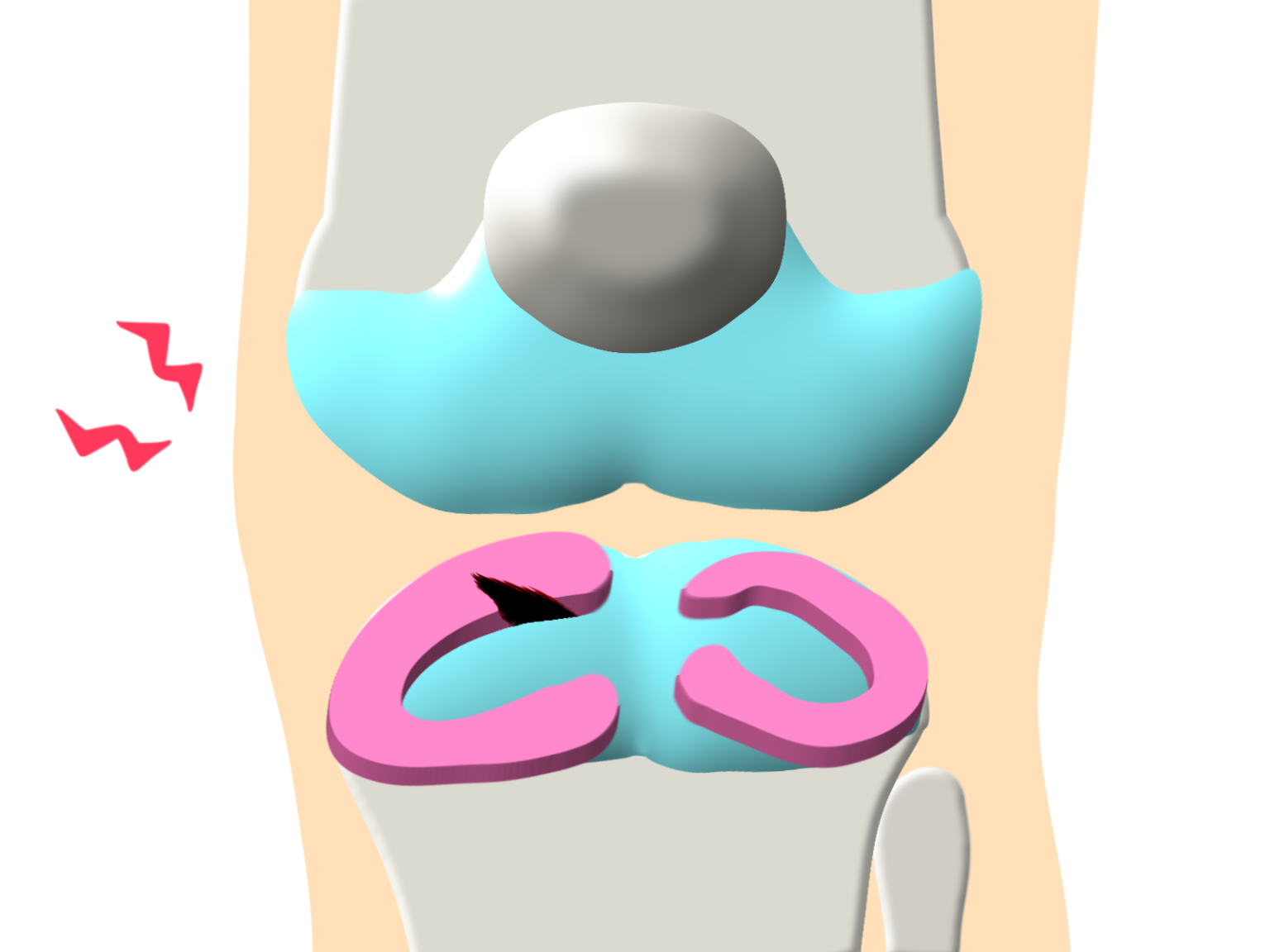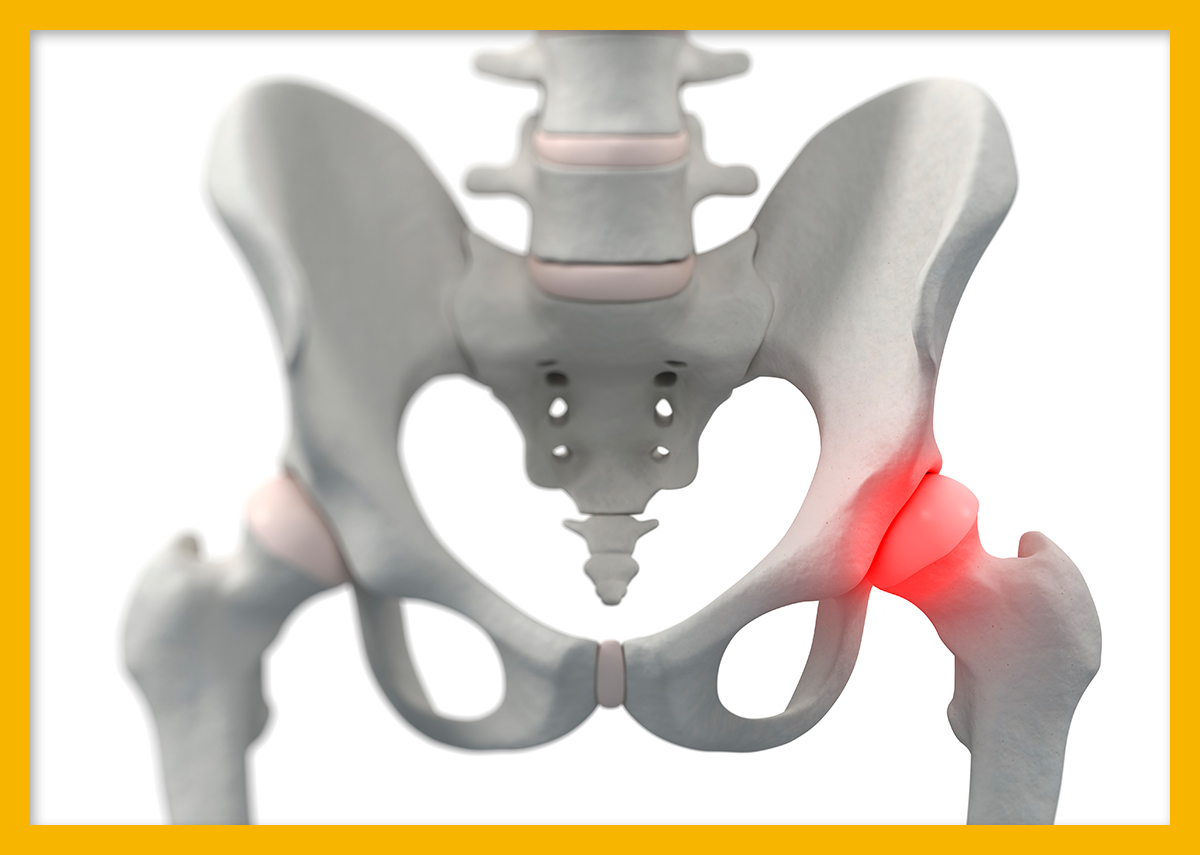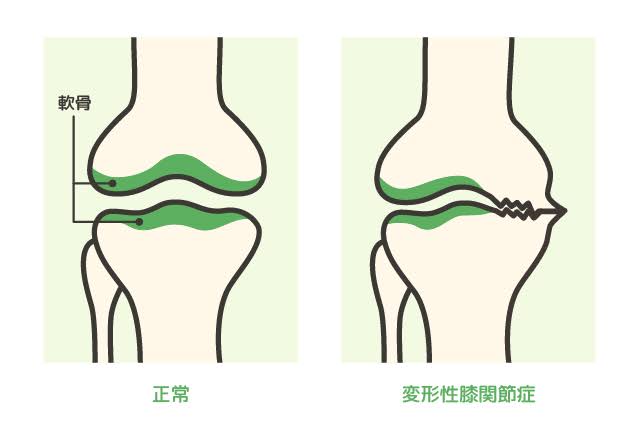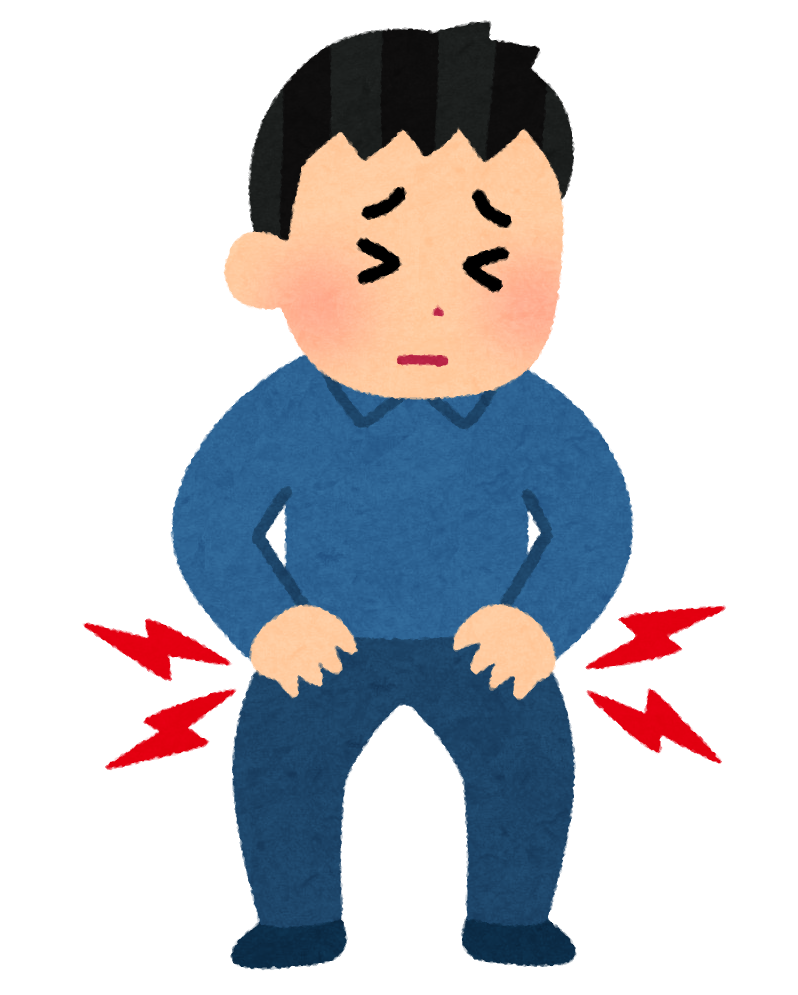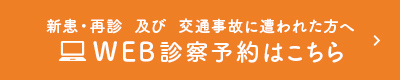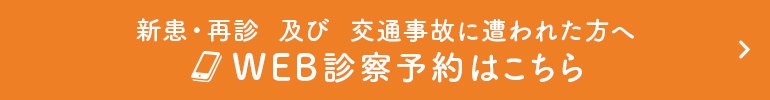人間の身体においては重さにして約60%を水分が占めています。脱水症は、この水分が不足した状態です。
普通は脱水状態になると喉が乾くので水を飲むなどして、水分補給を行います。
しかし、高齢者は喉の渇きを感じにくいという事があり、また小さな子供は喉の渇きを訴えられなかったり、自分で水を飲めなかったりするので、脱水症になりやすいので、注意が必要です。
脱水症の一般的な症状としては、 のどの渇きや 尿の減少 、肌や口の中などの乾燥があります。 脱水が進んでいくと、立ちくらみや頭痛、吐き気、筋肉の痙攣などが起きる場合もあります。 さらに重症になると、意識障害や腎機能の低下に伴う多臓器不全が起こります。
こまめに水分補給を行い、不調を感じたら早めに休息を取りましょう。